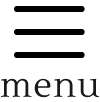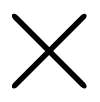お知らせ
- 2026-01(1)
- 2025-12(1)
- 2025-11(1)
- 2025-10(1)
- 2025-09(1)
- 2025-08(1)
- 2025-07(1)
- 2025-06(1)
- 2025-05(1)
- 2025-04(1)
- 2025-03(1)
- 2025-02(1)
- 2025-01(2)
- 2024-12(1)
- 2024-11(1)
- 2024-10(1)
- 2024-09(1)
- 2024-08(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(1)
- 2024-05(1)
- 2024-04(1)
- 2024-03(1)
- 2024-02(1)
- 2024-01(2)
- 2023-12(2)
- 2023-11(1)
- 2023-10(1)
- 2023-09(1)
- 2023-08(1)
- 2023-07(1)
- 2023-06(1)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(1)
- 2023-02(1)
- 2023-01(2)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(1)
- 2022-09(1)
- 2022-08(1)
- 2022-07(1)
- 2022-06(1)
- 2022-05(1)
- 2022-04(1)
- 2022-03(1)
- 2022-02(1)
- 2022-01(2)
- 2021-12(1)
- 2021-11(1)
- 2021-10(1)
- 2021-09(1)
- 2021-08(1)
- 2021-07(1)
- 2021-06(1)
- 2021-05(1)
- 2021-04(1)
- 2021-03(1)
- 2021-02(1)
- 2021-01(1)
- 2020-12(1)
- 2020-11(1)
- 2020-09(1)
- 2020-08(1)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(1)
- 2020-04(1)
- 2020-03(2)
- 2020-02(1)
- 2020-01(1)
- 2019-12(1)
- 2019-11(1)
- 2019-10(1)
- 2019-09(1)
- 2019-08(1)
- 2019-07(1)
- 2019-06(1)
- 2019-05(1)
- 2019-04(1)
- 2017-07(2)
- 2017-03(3)
2025/12/12
年末に見直したい! 我が家の冬の防災
年末は、家の中を整える機会が自然と増える時期です。そのため、防災ストックの確認や点検を行うには、ちょうどよいタイミングといえます。
12月8日に発生した青森県東方沖を震源とする地震では、5道県で9,282人が避難し、51人の負傷者が出ました。真冬の災害ということもあり、停電や断水が長引く可能性や、暖房が使えない状況を想像して「冬の防災をもう一度見直さなくては」と感じた方も多いのではないでしょうか。
安心して新年を迎えられるよう、ぜひ一度、防災ストックと設備まわりを見直してみませんか。
冬季に見直したい防災ストックは?
まず、飲料水やレトルト食品、カップ麺などの賞味期限、カセットボンベの残量や使用期限を確認しましょう。
卓上コンロは停電時でも使えるため、冬場の調理手段として大いに役立ちます。電気が止まるとIHクッキングヒーターやエアコンが使えなくなるため、「電気だけに頼らない備え」を持っておくことが大切です。
また、懐中電灯やモバイルバッテリー、携帯ラジオ、防寒用の毛布やカイロなど、寒さと暗さへの備えも見直しましょう。
冬季は気温低下が早く、停電した住宅では体温を奪われやすいため、保温できるアイテムが多めにあると安心です。
ガス漏れ警報器や住宅用火災警報器には交換期限があります。年末の「安全チェック」のひとつとして、そろそろ交換時期ではないかを確認してみてください。
屋外に設置されている給湯器やボンベまわりについては、落ち葉や雪、倒れやすい物がないかといった“環境の確認”だけでも十分です。
防災は、特別な取り組みではなく、日常を少し整えることの延長線上にあります。無理のない範囲で、ご家庭の備えを点検してみてはいかがでしょうか。
「エネルギーの備え」についても考えよう
皆様に普段からお使いいただいているLPガスは、災害時にも比較的早く復旧できるエネルギーとして知られています。
ボンベ単位で独立しているため、都市ガスのように広範囲の地下配管が止まる心配がなく、建物ごとに安全確認を行いながら順次供給を再開できます。
停電が発生しても卓上コンロや一部のガス機器が使えるため、温かい食事を確保できる点は大きな安心材料です。
とくに冬は、温かい食事やお湯が生活を支える力になります。非常用のカセットガスや卓上コンロを備えておくことで、いざというときの選択肢が広がります。
「エネルギーの備え」というと大げさに感じるかもしれませんが、日々の暮らしの中で少し意識を向けるだけで、防災力は大きく高まります。
LPガスの安全利用や非常時の備えについて気になることがありましたら、
どうぞお気軽にご相談ください。
2025/11/13
ガスの床暖房で、冬の暮らしをもっと快適に
暖房をつけているのに足元だけ冷たい、床に触れるとヒヤッとする――そんな冬のストレスを根本から解消してくれるのが、ガスの床暖房です。
足元からじんわり、太陽にあたるような自然なあたたかさ
ガスの床暖房の魅力は、とにかく「足元が冷えない」ということ。
床全体を均一に温め、その熱がゆっくりと体へと届きます。このときに伝わる熱は“輻射熱”と呼ばれ、太陽の光を浴びたときのポカポカした感覚と同じように熱が伝わるのが特徴です。
ストーブやエアコンのように温風を当てて空気だけを温める方法とは違い、体の表面と内部が少しずつ温まっていくので、芯からぽかぽか。風が出ないため、乾燥しにくく、ホコリや花粉、ペットの毛を舞い上げないのも大きな安心ポイントです。
喉がカラカラする、顔だけ暑い、暖房の風が苦手、という方にも向いています。
また、床暖房は床一面が“熱源”なので、部屋のどこにいてもムラが少なく、空間全体が包み込まれるような心地よさが続きます。
ソファでくつろぐとき、ダイニングで座るとき、キッチンに立っているとき、子どもが床で遊ぶとき…どんな姿勢でも足元からやさしく温かい。フローリングでも畳でも、どこに触れてもヒヤッとしないため、冬場の家事や育児のストレスも自然と軽減されます。
一般的な暖房では「部屋は温まってきたのに足先はずっと冷たい」ということがありますが、床暖房ではその心配がありません。
まず足元がしっかり温まり、その熱が体へ届くため、冷え性の方にもとても相性が良い暖房です。「寒いと無意識に肩が上がる」「家の中でも厚着してしまう」といった冬の不快感が驚くほど少なくなるのは、床暖房ならではのメリットです。
静かでクリーン、空気を汚さない快適暖房
床暖房は“風が出ない暖房”のため、運転中の音がほとんどなく、とても静か。テレビの音を邪魔したり、寝ている子どもを起こしたり、夜間に作動音が気になる心配もありません。また、温風で空気を巻き上げないので、長時間つけっぱなしにしても快適に過ごせます。
暖かさが空間を満たすように広がるため、部屋全体の温度差が小さく、リビングとダイニング、部屋の中心と隅、ソファとキッチンなど、場所による“寒い・暑い”の差が出にくいのも大きな利点です。
とくにガス式は温水を循環させて床全面を均一に温めるため、リビングなど広い空間でも足元からしっかり暖められ、家族みんながどこにいても同じように暖かさを感じられます。家族がそれぞれ好きな場所でくつろいだり作業したりしても、均一な暖かさが維持されます。
もちろんお部屋で一緒に過ごすペットにも快適で、床に直接横になっても冷えにくく、冬場でも居心地の良い環境がつくってあげることができます。
実際に設置したご家庭からは、「エアコンを使う時間が減った」「帰宅すると家全体がほんのり暖かい」「子どもが床で遊べるようになった」といった声も多く、生活の質が変わる暖房として人気が高まっています。
また、必要に応じて、スイッチオンですぐに暖まるガスファンヒーターを併用すると、短時間で一気に暖めたいときにも便利。スピード暖房と床暖房のやさしい暖かさを合わせることで、無理なく快適な室温を保つことができます。床からしっかり温まることで体感温度が上がり、室温設定を控えめにしても過ごしやすいため、省エネにもつながりやすいのがうれしいポイントです。
この冬、ぜひガスの床暖房でふんわりやさしい暖かさを体感してみてください!!
2025/10/14
変わりやすい秋の体調管理術 冷え・乾燥に負けない生活習慣を
朝晩の冷え込みと乾燥が気になり始める秋は、体調を崩しやすい季節です。寒暖差や空気の変化に負けないためには、日々の暮らしの中でちょっとした工夫が大切です。この記事では、秋に特有の「冷え」と「乾燥」への対策を中心に、体調を整えるための生活習慣をご紹介します。体の内外からしっかりケアして、季節の変わり目も快適に過ごしましょう。
冷えを防いで「めぐりのいい体」へ 服装・入浴・食習慣を見直そう
夏の疲れが残るなか、朝晩の冷え込みが日に日に増してくる秋。体調を崩す人が多くなるこの季節、特に気をつけたいのが「冷え」による不調です。寒暖差が大きくなることで自律神経のバランスが乱れ、免疫力の低下や睡眠の質の低下、さらには消化不良や肩こりといった症状も引き起こされやすくなります。まず実践したいのは、服装の見直し。体感温度が下がる前に、軽く羽織れるカーディガンやストールなどを持ち歩くと、体温の維持がしやすくなります。とくに、首・手首・足首の「三首」を冷やさないよう意識すると、全身の巡りもよくなります。
シャワーで済ませがちだった入浴習慣も、湯船に浸かることで秋の体調管理に大きく貢献します。ガスで沸かしたお風呂は温度が安定しており、38〜40℃程度のぬるめのお湯に10〜15分ゆっくり浸かれば、体の芯からじんわり温まるだけでなく、副交感神経を優位にしてリラックス効果も高まります。入浴後は湯冷めを防ぐために靴下や腹巻きで保温をしましょう。
さらに、体の内側から温める食習慣も大切です。しょうが、にんじん、かぼちゃ、長ねぎ、れんこんなどの体を温める食材を使った料理を積極的に取り入れましょう。具だくさんの味噌汁や煮込み料理は、手軽に栄養も摂れ、冷え対策にも最適です。夏に好んでいた冷たい飲み物や生野菜のサラダは控えめにして、常温の水や白湯、温かいお茶をこまめに摂ることで、内臓の冷えも和らぎます。「冷えは万病のもと」といわれるように、早めの対策で秋を健やかに乗り切りましょう。
乾燥に負けない体作り 肌・のど・空気の潤いを守ろう
秋が深まるにつれ、空気の乾燥も進み、肌荒れや喉の不快感、風邪などのトラブルが増えてきます。
とくに外気の乾燥に加え、エアコンや暖房による室内の乾燥も影響するため、「潤い対策」が体調管理の重要なポイントになります。まずできることは、加湿環境の整備です。加湿器の使用はもちろん、就寝時には濡れタオルを部屋に干すだけでも湿度は改善します。また、観葉植物を置くのも自然な加湿効果が期待できる方法です。
乾燥を感じにくい暖房方法としては、床暖房の導入もおすすめです!
風を使わずに足元からじんわりと温めるため、空気が乾燥しにくく、肌や喉への刺激が少ないのが特長です。家の中でも快適に過ごす工夫として、秋冬に向けてぜひ検討してみてください。
肌や喉の乾燥には、外側からのケアと内側からのケアをバランスよく行うことが必要です。スキンケアは保湿力の高いアイテムに切り替え、洗顔後や入浴後すぐの「3分以内保湿」を心がけると乾燥を防げます。外出時にはマスクを活用して喉や鼻の粘膜を守るのも有効です。水分補給は夏よりも忘れがちになりますが、体内の潤いを保つには季節を問わず重要です。冷たい飲み物ではなく、常温の水や白湯、ハーブティーなどを意識的に摂るようにしましょう。
また、秋の果物には乾燥対策に役立つ栄養素が豊富です。梨や柿には水分とともに喉を潤す作用があり、ぶどうやりんごはビタミンやポリフェノールを含み、肌の健康にも役立ちます。さらに、質の良い睡眠を取ることも免疫力を保ち、乾燥による風邪予防につながります。寝る直前のスマホは避け、部屋の照明を落として心身をリラックスさせる工夫を。秋は「気づかないうちに不調が進んでいる」ことが多い季節。だからこそ、少しの意識と工夫で大きな変化を感じられる時期でもあります。
2025/09/12
秋の味覚をもっとおいしく! ガス火で楽しむ旬の料理
まだまだ厳しい暑さが続き、残暑のきびしさを感じる9月。それでも季節は少しずつ秋へと移ろい、店頭にはサンマやさつまいも、きのこ、栗など、秋ならではの味覚が並びはじめます。暑さに疲れた体をいたわりながら、旬の食材で食卓に秋の彩りを取り入れてみませんか。ガス火ならではの強い火力や直火調理を活かせば、素材の旨みを引き出し、秋の味わいを一層楽しめます。
ガス火だからこそ味わえる“秋のごちそう”
秋は夏の疲れが出やすい時期ですが、同時に「食欲の秋」といわれる季節でもあります。
サンマ、さつまいも、栗、きのこなど、秋に旬を迎える食材は、栄養豊富で味わい深いものばかり。体調を整えながら、季節を感じられる食卓を彩ってくれます。
こうした旬の食材をよりおいしく仕上げるのに欠かせないのが、ガス火の調理力。直火の強い熱でサンマを焼けば、皮はパリッと香ばしく、中身はふっくらジューシー。煙やニオイを抑えて焼ける魚焼きグリルなら、後片付けも簡単です。きのこは強火で一気に炒めることで水分を飛ばし、香りを立たせるのがポイント。バター醤油やガーリック風味に仕上げれば、ご飯もお酒もすすむ一品になります。
また、秋のスイーツもガス火と相性抜群。さつまいもは弱火でじっくり加熱することで、でんぷんが糖に変わり、甘さが増して“蜜たっぷり”の焼き芋に。電子レンジではなかなか出せない、ほっこりした甘みが引き立ちます。栗は圧力鍋を使えば短時間でホクホクに仕上がり、手軽に栗ご飯や甘露煮が楽しめます。ガス火調理の特長である「強火」と「じっくり弱火」を使い分けることで、秋の味覚が一段と豊かに感じられるでしょう。
旬の食材を「旬のうちに」楽しむことは、栄養面でもメリットが大きいといわれています。季節の食材をガス火でおいしく調理し、心と体を秋のリズムに整えていきましょう。
安心&便利! Siセンサーコンロで広がる調理の楽しみ
「ガス火はおいしいけれど、焦がしてしまいそうで不安」「火加減がむずかしい」と思われる方も少なくありません。
そんな不安を解消してくれるのが、最新のSiセンサーコンロです。
Siセンサーコンロは、鍋底の温度を自動で感知し、必要に応じて火力をコントロールしてくれる優れもの。揚げ物なら設定温度をキープしてカラッと仕上げ、炒め物は高温になりすぎるのを防いでシャキッとした食感を残してくれます。煮物をしていても、吹きこぼれそうになれば火を弱めて調整してくれるので、焦げつきやコンロの汚れを防ぎ、後片付けもラクになります。
さらに便利なのがタイマー機能。グリルで焼くサンマも、セットしておけば焦げる心配なく、ちょうどよい焼き加減に仕上がります。毎日の調理をサポートするこうした機能は、忙しい共働き世帯や子育て世代にこそ心強い存在です。
Siセンサーコンロは安全面でも大きな進化を遂げています。万が一、鍋が空焚き状態になったり、火が消えたりした場合には自動でガスを遮断。小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭でも、安心してガス火を活用できます。
「強火の魅力」と「安心の安全機能」を兼ね備えたSiセンサーコンロがあれば、旬の食材をより気軽に、より安心して楽しむことが可能です。この秋はぜひ、ガス火の良さを再発見しながら、季節のごちそうを食卓に並べてみませんか。

秋の簡単レシピ
さつまいもときのこのバター醤油炒め(2人分)
材料:
さつまいも:1本(200gほど)
しめじ:1/2パック
えのき:1/2パック
バター:10g
醤油:大さじ1
みりん:大さじ1
塩・こしょう:少々
青ねぎ(あれば):適量
作り方:
1,さつまいもは皮付きのままよく洗い、薄めの輪切りにして水にさらします(5分程度)。
2,しめじとえのきは石づきを取り、小房に分けておきます。
3,鍋に水を入れてさつまいもを5分ほど下ゆでして柔らかくしておきます。
4,フライパンにバターを熱し、さつまいもを炒めます。
5,きのこを加えてさらに炒め、しんなりしたら醤油とみりんを回し入れます。
6,味を見て塩・こしょうで整え、仕上げに青ねぎを散らして完成!