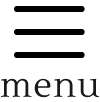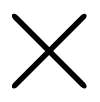お知らせ
- 2025-08(1)
- 2025-07(1)
- 2025-06(1)
- 2025-05(1)
- 2025-04(1)
- 2025-03(1)
- 2025-02(1)
- 2025-01(2)
- 2024-12(1)
- 2024-11(1)
- 2024-10(1)
- 2024-09(1)
- 2024-08(1)
- 2024-07(1)
- 2024-06(1)
- 2024-05(1)
- 2024-04(1)
- 2024-03(1)
- 2024-02(1)
- 2024-01(2)
- 2023-12(2)
- 2023-11(1)
- 2023-10(1)
- 2023-09(1)
- 2023-08(1)
- 2023-07(1)
- 2023-06(1)
- 2023-05(1)
- 2023-04(1)
- 2023-03(1)
- 2023-02(1)
- 2023-01(2)
- 2022-12(1)
- 2022-11(1)
- 2022-10(1)
- 2022-09(1)
- 2022-08(1)
- 2022-07(1)
- 2022-06(1)
- 2022-05(1)
- 2022-04(1)
- 2022-03(1)
- 2022-02(1)
- 2022-01(2)
- 2021-12(1)
- 2021-11(1)
- 2021-10(1)
- 2021-09(1)
- 2021-08(1)
- 2021-07(1)
- 2021-06(1)
- 2021-05(1)
- 2021-04(1)
- 2021-03(1)
- 2021-02(1)
- 2021-01(1)
- 2020-12(1)
- 2020-11(1)
- 2020-09(1)
- 2020-08(1)
- 2020-07(1)
- 2020-06(2)
- 2020-05(1)
- 2020-04(1)
- 2020-03(2)
- 2020-02(1)
- 2020-01(1)
- 2019-12(1)
- 2019-11(1)
- 2019-10(1)
- 2019-09(1)
- 2019-08(1)
- 2019-07(1)
- 2019-06(1)
- 2019-05(1)
- 2019-04(1)
- 2017-07(2)
- 2017-03(3)
2024/06/13
おいしく健康に♪夏バテに効くメニューを知りたい!
夏バテ予防に効果的な栄養素は?
すっかり暑い日が続くようになってきました。暑くなってくると起こりやすい夏バテとは、体がだるかったり、食欲がなくなってしまう症状のこと。原因としては、夏の室内外の温度差に体がついていけず、自律神経の動きが乱れてしまうことにあります。また大量の発汗により、水分やミネラルが喪失してしまい、脱水傾向に陥ってしまうということもあります。
夏バテ予防に効果的な栄養素は、ビタミンB1、ビタミンB2、タンパク質、ミネラルなどがあげられます。それぞれの栄養素を多く含む食品は以下のとおりです。
ビタミンB1を多く含む食品:豚肉、うなぎ、玄米、ごまなど
ビタミンB2を多く含む食品:レバー、うなぎ、牛乳、納豆など
タンパク質を多く含む食品:肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品など
ミネラルを多くふくむ食品:食塩、野菜・果物類、乳製品、海藻類、レバー、煮干しなど
おいしく食べて夏バテを予防しよう!
夏バテ予防にぴったりのメニュー「ぶっかけそうめん」をご紹介します。
そうめんは手軽なうえ、アレンジが無限大の優秀レシピ!さまざまな具材をのせることで、栄養バランスや夏バテ予防にもばっちりです。
麺つゆにつけて食べるいつものやり方ではなく、たくさんの具材をのせて麺つゆを上からかけるスタイルなら、栄養も偏らずにばっちりです。
かけるのは麺つゆだけでもおいしいですが、ゴマ油や炒りごまなどを加えてもおいしいですよ♪
<おすすめ具材>
ぜひお気に入りの組み合わせを見つけてみてください♪
豚肉(ゆで)/鶏むね肉(ゆで)/なす(焼き、揚げ)
トマト/オクラ/ミョウガ・/キュウリ/海藻/梅干し
アボカド+まぐろorエビ/納豆+キムチ/サバ缶+青じそ/ツナ+塩こんぶ
<そうめんの上手な茹で方>
・お湯はたっぷり沸かす(2束100gで1リットルが目安)
・沸騰したらそうめんを入れて軽くほぐす(1分30秒~2分が目安)
・再沸騰したら火をとめてふたをし、5分放置(麺にはさわらない)
・氷水でしめて、しっかりとヌメリをとる
ポイントは、たっぷりのお湯を使うことと、ヌメリをしっかりととること。ヌメリが残っていると、くっつきやすくなってしまいます。
2024/05/13
5月が最適! “梅雨じたく”はじめませんか?
2024年の暦上の梅雨入りは6月10日。平年並みであれば、6月上旬には梅雨がスタートします。
そこで5月のうちにはじめておきたいのが“梅雨じたく”。
蒸し暑くじめじめとした梅雨シーズンを少しでも快適に過ごすために、いまのうちに準備をしておきませんか?
5月のうちにやっておきたい梅雨じたく
梅雨じたくには、たとえば以下のようなことがあります。
・衣替えと風通し
じめじめとし始める前に、夏服への移行を始めましょう。
冬の間締め切っていたクローゼットや押し入れの扉を開け放して、換気をすることもおすすめです。
・大物の洗濯物
いつものお洗濯に加え、カーテンやソファカバーなどの大物はこの時期に洗濯するのがベスト。冬物から夏物にイメージチェンジするのもいいですね。
・雑草のお手入れ
家まわりの雑草は、梅雨時期には大きく成長してしまうものも。いまのうちに根っこから抜いておくと、後がラクです。
スピーディでパワフル!便利なガス機器をぜひ使ってみてください
ご家庭内における梅雨のお悩みナンバーワンともいえる“お洗濯”。
生乾きやニオイの対策は、ぜひガスの力で解決してください!!
電気式のものでは時間がかかったり、パワーが足りない…なんてことも。その点、ガスなら大丈夫。
パワフルな温風で、梅雨の悩みも湿気と一緒に飛ばしてしまいます♪
・ガス衣類乾燥機
6kgの洗濯物をたった1時間で乾かしてくれるガス衣類乾燥機。
すごいのはそのスピードだけでなく、ニオイのもととなる菌の減少率がなんと99.9%!
そのため、コインランドリーで採用されている衣類乾燥機はほとんどがガス式なのです。
ガスならではのパワフル温風で、お日様のもとに干すよりもふっくら仕上げてくれますよ♪
・ガス浴室暖房乾燥機
「洗濯物もさっと乾かしたいし、お風呂も快適に入りたい!」というご家庭におすすめなのが浴室暖房乾燥機です。
洗濯物をお風呂に干せるのはもちろん、浴室のカビ菌発生を抑えてくれるから、お風呂掃除がとってもラクになります。
もちろん、冬場はお風呂の暖房として大活躍。1年中、お風呂を快適空間にしてくれます。
プラズマクラスター搭載の機種もあります。
2024/04/15
毎日使うところだから……トイレをお気に入り空間にしませんか?
日本のトイレは世界一!?
日本の水洗トイレの始まりは1900年代、大正時代にまで遡ります。1960年代には温水洗浄便座が登場し、1990年に空間をすっきりとさせるタンクレスが普及し始めました。
日本のトイレ技術は世界一といわれており、公衆トイレですら温水洗浄機能がついており、自動で水が流れてくれる国はそう多くありません。
もちろん、家におけるトイレも年々進化をしています。
そんな家のトイレ、入ると「落ち着く、リラックスできる」と思っている方も多いのではないでしょうか。
人は1日に5~7回ほどトイレに行くと言われています。仕事や学校、外出先もふくまれますから、ご自宅での利用は朝晩のみという方も多いかもしれませんが、毎日のように利用する場所には違いありません。
私たちの“リラックスの場”であるトイレを、より快適に、お気に入りの場所にしてみませんか?
こだわりのトイレ空間をつくりませんか
日常的に過ごすことの多いリビングやキッチン、寝室は、やさしく無難な色合いにまとめることが多い場所です。
だからこそ、逆にトイレはこだわりを詰められるところ!
毎日使う場所だから、入るたびにうきうきわくわくする場所にしてみませんか?
素敵だけれど、リビングや寝室にはちょっと派手かも……というような壁紙や床、照明も、トイレならいいかもしれません。
もちろん機能面でも、ふた自動開閉、自動便器洗浄、泡洗浄、スマホ対応などといった高機能化も進んでいます。
本体だけでなく、ライフステージに合わせて段差解消や手すり付きも考えていきたいところです。
選ぶときのチェックポイントは、本来の洗浄機能に加え、節水・節電、除菌・汚れ防止、お掃除のしやすさ、それに価格など、さまざま。ぜひ、ご相談ください!
2024/03/13
いざというときの備えにも!ガスコンロでできる“火育”を考えてみよう
“火育”という言葉を知っていますか?
火育とは、人間の歴史において、とても大きな役割を果たしてきた火について、その正しい知識や重要性を学ぶことをいいます。
ところが近ごろは、ご自宅に仏壇のマッチやろうそく、たき火などの風景が消えつつあります。
それにより、子どもたちが火について学ぶ機会が極端に少なくなっているのです。
つまり、ガスコンロは家庭内で直火を扱うことができる貴重な存在でもあるのです!
もちろん、火の危険性を伝えることは重要です。
そして、それと同時に、安全・安心に使えるように教えることも、とても大切なことです。
また安全な火の使い方を知ることは、災害の備えとしても有効です。
マッチやろうそくの使い方だけでなく、いつもは電気炊飯器で炊くご飯を直火=ガスコンロでも炊いてみて、分量や時間の配分を覚えておけば、いざというときの備えになります。
防災の備えとしてカセットコンロを用意しておけば、万が一ライフラインが止まってしまったときも、あたたかいご飯を炊いて食べることができますよ。
土鍋がない場合も、フライパンや鍋でもご飯を炊くことができます。
また、ガスコンロでおいしいご飯をつくることは、火育に限らず、食育にもなります。
自分たちの手で調理したご飯を、おいしく食べることがもたらしてくれる幸せを、ぜひご家族で体験してみてください。
小さなお子様が火を扱う際は、必ず大人の方が付き添ってくださいね。
ガスコンロでご飯を炊こう
お子様がガスコンロを使うタイミングは、普段の料理のお手伝いでもいいですが、まずはぜひご飯を炊いてみることをオススメします。
ガスでご飯を炊くと、炊飯器では味わえない、ぴかぴか、もちもちのお米に! ガスならではの直火で、ご飯をおいしく仕上げてくれるのです。
土鍋でご飯を炊いた場合は、そのまま食卓へ。テーブルで取り分けたら、よりおいしく感じるかも? 特別なごちそう感を演出してくれます♪
ガスコンロでご飯を炊く方法は、以下を参考にしてみてください。
準備するもの
・土鍋(ふたつきフライパンや鍋でも可)
・お米3合(4~5人分)
・水(適宜)
・ガスコンロ(カセットコンロでも可)
・ボウル(浸水用)
※土鍋はガスコンロ専用のものを使用してください
炊き方
1:お米をとぐ(やさしくかき混ぜる)
2:お米に浸水させる*(夏場は30分、冬場は1時間)
3:土鍋にお米を移しふたをしたらガスコンロにかけ、強めの中火で沸騰させる(10分程度)
4:沸騰したら弱火にして、10分加熱を続ける
5:火を消して10分蒸らす
*土鍋で浸水させるとヒビの原因になるため、ボウルを使ってください
2024/02/13
花粉症にはつら~い季節がスタート…そんなときにはガス衣類乾燥機がオススメです♪
花粉症の対策は?
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、充血……花粉症にはつらい季節が始まりました。
花粉症は春の花粉が原因となっていることが多く、そのなかでも70%がスギによるものといわれています。
スギは年初から飛び始めて3月にピークを迎え、5月くらいまで飛散します。
またヒノキは4月にピークを迎え、6月くらいまで飛散します。
花粉症の症状を抑えるには、医師の診断のもと対症療法を行うなどがありますが、日々の生活でも取り入れられる対策があります。
◎お部屋に入る前にコートや上着を脱ぐ
外から帰ってきた際、衣類に着いた花粉を持ち込まないよう、上着を脱いで花粉をはたいてからお部屋に入りましょう。
◎換気は午前中に行う
花粉のピークは12時頃と夕方頃といわれています。換気をする場合は、飛散量の少ない午前中に短時間で行いましょう。
◎適切な湿度を保つ
しっかり加湿することで、室内に入り込んだ花粉が水分を含み、重みで床へと落下します。室内の湿度を40~60%に保つようにしましょう。
ガス衣類乾燥機が活躍します!
衣類に付着し、室内に持ち込まれてしまう花粉。洗濯ものを外干ししていると、せっかく洗った衣類にも花粉がついてしまいます。
洗濯を終えたら、洗濯ものはそのままガス衣類乾燥機へ。ガスならではのハイパワーで、あっという間にふわふわに仕上がりますよ♪
外を経由しないから花粉が付着する心配はありませんし、ニオイの原因となる生乾き臭もありません。
忙しい毎日の家事のなかで、「困った」「面倒くさい」を少しでも減らすために、ぜひガス衣類乾燥機をご検討ください!!